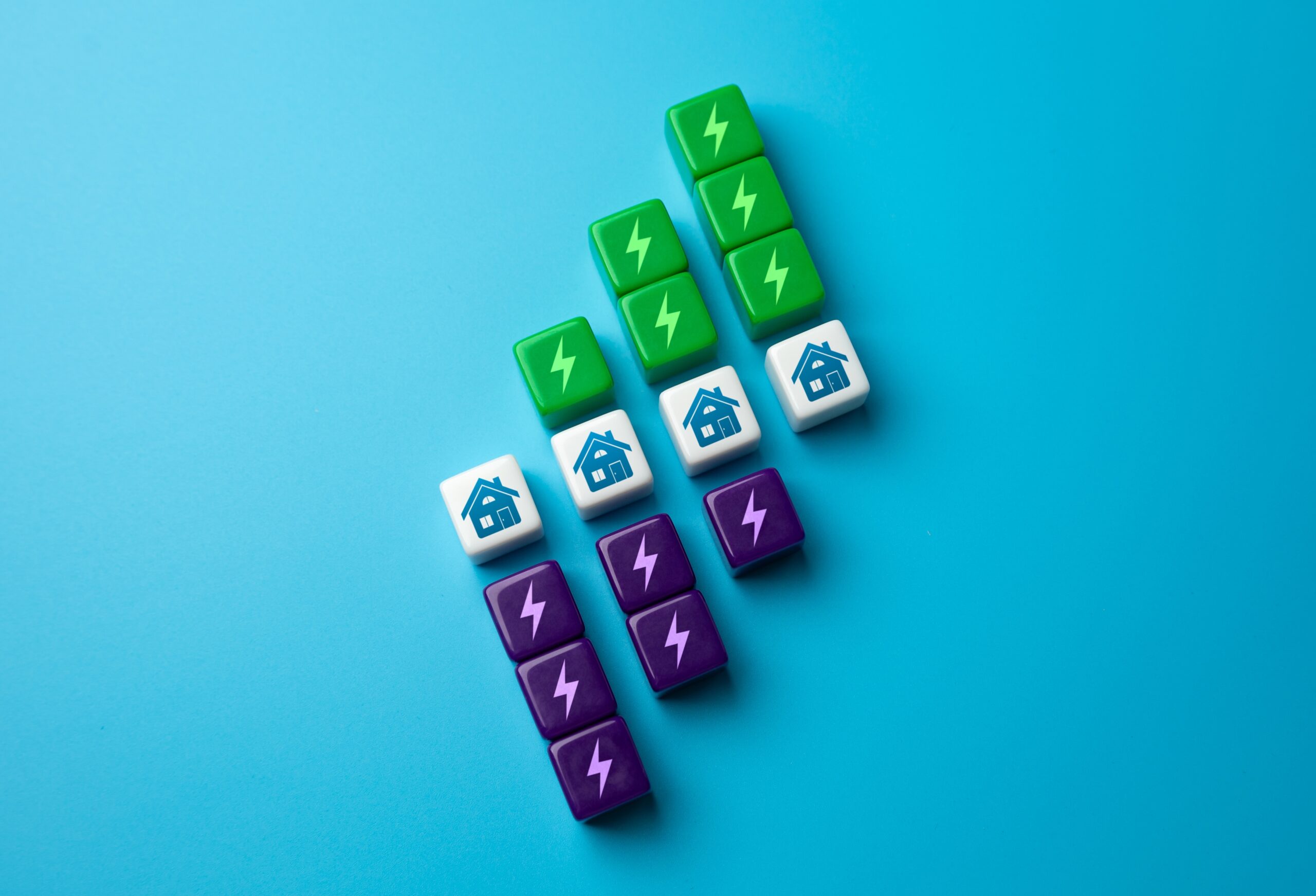近年、地震や台風などの自然災害に加え、エネルギー価格の高騰や電力需給ひっ迫といったリスクが顕在化する中で、法人施設における電源の「安定確保」は経営課題の一つとなっています。
特に事業継続(BCP)や設備保護、脱炭素対応を見据える企業にとって、非常時でも建物全体に電力を供給できる全負荷型蓄電池の導入は、今や選択肢ではなく戦略的投資の一環といえるでしょう。
従来の部分負荷型蓄電池では一部の回路のみがバックアップ対象でしたが、全負荷型では空調・通信・サーバー・照明・生産設備まで含めた「全館対応」が可能になります。
本記事では、全負荷型蓄電池の仕組みや技術的要点、導入事例とその効果、経済性と制度活用の観点から、法人にとっての最適な導入のあり方を詳しく解説します。
全負荷型蓄電池とは何か?法人施設に求められるエネルギー対策
電力の安定供給が企業活動に与える影響は年々大きくなっています。特に、自然災害の多発やエネルギー価格の変動により、法人施設における停電対策やエネルギー自立の重要性が増しています。こうした背景のもと注目されているのが「全負荷型蓄電池」です。
全負荷型とは、建物全体の電力負荷をカバーできる蓄電池システムを指し、非常時でも通常と同様の業務を継続できる点が最大の特徴です。従来の部分負荷型と比較して、より広範囲な電力供給を可能にすることから、BCP(事業継続計画)の中核として導入が進んでいます。
全負荷型と部分負荷型の基本的な違い
部分負荷型蓄電池は、停電時にあらかじめ設定された特定の回路や機器だけに電力を供給する方式です。一般的には照明や一部のコンセント、サーバーラックなど最低限の設備に限定されます。
一方、全負荷型蓄電池は建物全体、またはフロア単位の電力をバックアップ可能な構成となっており、空調・エレベーター・大型機器などを含めた電源供給が可能です。電源切替も自動で行えるため、業務への影響を最小限に抑えた運用が期待できます。
事業継続計画(BCP)と全館バックアップの必要性
災害発生時の事業停止は、企業にとって重大な損失をもたらします。全負荷型蓄電池を活用することで、停電中でもオフィスや工場の全館稼働を維持でき、重要業務の継続やデータ損失の防止に直結します。
BCPを策定している企業の多くは、非常用発電機やUPSと併用しながら、全負荷型の蓄電池を組み合わせることで、より柔軟かつ持続的な電源確保体制を整備しています。特に24時間稼働の物流拠点や医療機関、自治体施設などでは、全館対応の必要性が高まっています。

系統用蓄電池としての全負荷対応型の特徴
全負荷型の蓄電池は、系統連系型として運用されるケースも増えています。通常時は電力系統と接続し、ピークカットや電力需給調整などの機能を果たしつつ、非常時には独立運転モードへ自動切替される設計です。
また、VPP(仮想発電所)やネガワット取引への参加も視野に入れた高度なEMS(エネルギーマネジメントシステム)との連携が進められており、単なる非常用電源の枠を超えて、収益性のあるエネルギー資産として活用されつつあります。
法人施設における全負荷型蓄電池の活用メリット

全負荷型蓄電池の導入は、停電対策としての有効性に加え、エネルギーコスト削減や脱炭素対応など、企業活動全体に好影響を与える戦略的な投資といえます。
停電・災害時における業務継続の確保
気象災害や事故による停電時にも、業務を継続できる環境を構築することは、取引先や顧客との信頼維持に直結します。たとえば、IT企業においては、システムダウンが数分でも業務全体に大きな支障をもたらす可能性があり、こうしたリスクへの備えとして、全負荷型蓄電池は強力なソリューションです。
さらに、電力供給の安定性は従業員の安全確保にも関係します。停電時の避難誘導や照明維持、情報通信手段の確保など、全館への電力供給によって企業としての防災体制を強化できます。
重要インフラ設備(空調・通信・サーバー等)の常時稼働
特定の機器だけを守る部分負荷型では対応が難しい、空調や大型サーバー設備、監視カメラシステムなどの“全体を支える基幹設備”も、全負荷型なら安定稼働が可能です。
特に通信・情報インフラの確保は、現代の企業活動において最優先事項のひとつです。停電時にネットワークが遮断されれば、業務の再開には相当な時間とコストを要します。全負荷型蓄電池を導入することで、こうしたリスクを回避し、継続的な業務体制を確保できます。
自家消費型太陽光との連携によるエネルギー自立性の向上
全負荷型蓄電池は、太陽光発電との相性が非常に良く、昼間に発電した電力を蓄電し、夜間や停電時に活用する「自家消費+非常用バックアップ」のハイブリッド運用が可能です。
電力購入量の削減だけでなく、エネルギーの地産地消を実現し、RE100や脱炭素経営に向けた取り組みにも貢献します。
また、災害時に系統からの電力供給が停止しても、太陽光発電と全負荷型蓄電池の組み合わせによって、建物全体のエネルギー供給を継続できる仕組みが構築できます。これは企業のレジリエンス強化という観点からも、大きな価値を持つ選択肢です。
導入にあたっての設計・技術的課題
全負荷型蓄電池を法人施設へ導入する際は、「理論上は動くはず」では済まされません。
高出力・大容量の運転を前提とするため、電気設備の設計段階で解決すべき技術課題が数多く存在します。
設備規模が大きいほど初期の吟味が甘いまま工事に入ると、後戻りコストが跳ね上がり、投資回収計画に深刻な影響を及ぼします。
高出力・大容量への対応と初期設計の重要性
全館バックアップを実現するには、瞬発的に数百キロワットからメガワット級の出力を扱うケースが珍しくありません。
蓄電池モジュールの直列・並列構成、PCS(パワーコンディショナー)の定格、保護系統の定格値などを早期に確定しないと、着工後にケーブルの太さや遮断器容量を見直す事態が発生します。
特に負荷変動の激しい工場やデータセンターでは、ピークカレント時の安全余裕を十分確保した上で、蓄電池の充放電制御を最適化する設計が欠かせません。
高圧受電施設での回路構成と切替制御
受電電圧が6.6kV以上の高圧需要家では、蓄電池を低圧側に入れるか高圧側に入れるかで回路構成が大きく変わります。
高圧側に接続する場合、トランス容量を増設するか、非常回路専用の開閉器を新設する必要があります。
逆に低圧側で分岐する場合は、切替スピードと負荷容量のバランス、逆潮流規制への適合が課題になります。
また、切替時の瞬断許容時間がサーバーや制御装置の要件を満たすかどうかも事前の検証ポイントです。
既存設備との整合性と制御システムの要件
全負荷対応型を後付けする場合、既存の非常用発電機、UPS、受変電設備にインターフェースを持たせる必要があります。
発電機と蓄電池の優先順位、系統連系リレーの動作設定、非常用回路の同期条件などを明確にし、BMS(バッテリー・マネジメント・システム)とEMS(エネルギー・マネジメント・システム)を統合監視できる構成を採ることで、運用オペレーターの負担を大幅に減らせます。
サイバーセキュリティ面では、リモート操作系統の通信暗号化やファームウェア更新手順を標準化し、長期運用時のリスクを最小化する仕組みづくりが求められます。
全負荷型蓄電池の活用で得られる経済的・制度的メリット

全負荷型蓄電池は「保険的コスト」だけにとどまりません。電力市場の制度改革と補助政策の拡充により、設備を積極的に収益化する選択肢が増えています。
災害対応・BCPを確保しつつ、経済合理性を持たせられる点こそが、近年導入が加速している最大の理由です。
需給調整市場・容量市場への参入可能性
2021年に本格稼働した需給調整市場と、2024年から容量市場の商用取引が本格化したことで、短時間の調整力や将来供給力を提供できる蓄電池に対する需要は急増しています。
全負荷型システムは高出力設計であることが多く、調整量の単位が大きい市場入札要件を満たしやすいという利点があります。
EMS経由でアグリゲーターに制御を委託すれば、施設側は運用負荷を抑えつつ市場収益を取り込むことが可能です。
ネガワット取引による新たな収益源の創出
ネガワット取引は、電力需要を抑制または出力を供給することで報酬を得るスキームです。
全負荷型蓄電池を併設した工場や物流センターは、ピークタイムに系統へ電力を返すことで、単なる節電では得られないインセンティブを享受できます。
特に夜間操業や24時間稼働ラインを持つ施設は、深夜電力で充電し昼間に放電する運転パターンと親和性が高く、需要家側にキャッシュフローをもたらす新たなビジネスモデルとして注目されています。
補助金・税制優遇措置の適用条件と活用例
経済産業省の「蓄電池導入促進事業」や環境省の「地域脱炭素投資促進事業」など、全負荷型蓄電池も対象に含む補助メニューは年々拡充しています。
補助率は設備費の3分の1から2分の1が一般的で、加えて法人税の特別償却や固定資産税の軽減措置が併用できるケースもあります。
実際、自治体庁舎や大型ショッピングモールでは、補助金と税制特例を併せて初期投資額を40%以上圧縮した事例が報告されています。
適用条件には、最低容量や系統連系要件、EMS連携の実証報告義務などが定められているため、事前に公募要領を精査し、申請スケジュールを設計・調達計画と同期させることが不可欠です。
補助枠の消化が早い年度もあるため、設備ベンダーやコンサルティング会社と連携し、確実に採択を狙う体制構築が成功の鍵となります。
法人向け全負荷型蓄電池の導入事例と効果
全負荷型蓄電池の導入は、非常時の対応力強化にとどまらず、平時における運用コストの最適化や電力の有効活用といった経済的な利点ももたらします。
ここでは、実際に導入が進んでいる法人施設や公共施設での活用事例を通じて、その効果を具体的に見ていきます。
工場・物流施設におけるBCP対策の強化例
ある大手製造業の工場では、停電時にも主要生産ラインを止めないために、全負荷対応の蓄電池を導入しました。
従来は非常用発電機を中心とした部分バックアップ体制でしたが、冷却装置や制御系統など、一部のインフラが停電で停止してしまうリスクがあり、生産再開までに数時間を要する状況が課題でした。
導入後は、工場全体に自動的に電力を供給できる体制を構築。系統連系型としたことで、通常時はピークカットやデマンド制御にも活用しており、年間数百万円規模の電力コストの削減にも成功しています。
また、蓄電池を活用した需給調整市場への参入も実施され、エネルギー部門を“収益を生む部署”へと転換する一助となっています。
物流業界でも、冷蔵倉庫や配送拠点への全負荷型蓄電池の導入が進んでいます。冷蔵設備は一度停止すると品質劣化リスクが高く、災害時の被害額が非常に大きくなるため、事業継続の観点からも全館対応の電源確保が強く求められています。
自治体・病院など公共施設での導入事例
災害時に地域住民の避難拠点となる市庁舎や公民館、また医療機能を担う病院・クリニックでも、全負荷型蓄電池の導入事例が拡大しています。
ある中規模自治体では、庁舎の全館に蓄電池を配備し、災害時でも照明・冷暖房・上下水ポンプ・通信設備を稼働させる体制を構築しました。
地域の防災拠点としての信頼性向上はもちろん、日常的にも太陽光発電との併用によって電力購入量を大幅に抑制できる運用モデルが確立されています。
医療分野では、救急医療や手術が求められる地域中核病院において、手術室・ICU・電子カルテサーバー・空調を含む病院全体をバックアップ対象とする全負荷型蓄電池が導入されています。
UPSやディーゼル発電機との併用で瞬断を防ぎ、停電時でも医療機能が維持される設計とされており、BCP強化と補助金活用の両面で高く評価されています。
導入後の電力コスト削減と運用の最適化
全負荷型蓄電池は、停電対策としての効果だけでなく、通常時の運用コスト削減にも寄与します。
電力使用量が大きい法人では、ピークカット(最大需要電力の抑制)やピークシフト(高額時間帯から安価な時間帯への移行)を実施することで、基本料金と従量料金の双方を引き下げることが可能です。
ある大規模オフィスビルでは、蓄電池を使って夕方のピークタイムの電力需要を削減。さらに、夜間の余剰太陽光電力を蓄えて翌日の消費に回す運用により、年間で契約電力の削減と合わせて10%以上の電力料金カットを実現しています。
また、EMSを活用した運用最適化によって、蓄電池の充放電スケジュールが自動制御され、エネルギー運用の属人化リスクも軽減されています。今後、電力価格の変動や脱炭素経営が進む中で、エネルギーの“見える化”と“最適化”をセットで推進できる点は、企業にとって大きな強みとなるでしょう。
まとめ|法人が全負荷型蓄電池を導入するべき理由と選定の視点
全負荷型蓄電池は、単なる停電対策にとどまらず、BCPの中核装置としての機能や電力市場への参入による収益化、エネルギー自立性の向上など、法人にとって多面的な価値をもたらします。
インフラ設備や業務機能を全館で継続させる必要がある企業・自治体にとって、その導入効果は極めて実用的かつ戦略的です。
一方で、設計段階では出力・容量の正確な見積もり、既存設備との連携設計、補助金制度との整合性など、多くの検討ポイントがあります。導入を成功させるためには、目的を明確にしたうえで、技術面・制度面・経済面を統合的に判断し、自社に最適なサイズ・仕様を見極めることが不可欠です。
将来のレジリエンス強化とエネルギー戦略の両立を目指す企業にとって、今まさに全負荷型蓄電池は“備え”ではなく“攻め”のインフラとして再評価されています。今後の設備計画において、ぜひ本記事の内容を実務判断の参考にしてみてください。