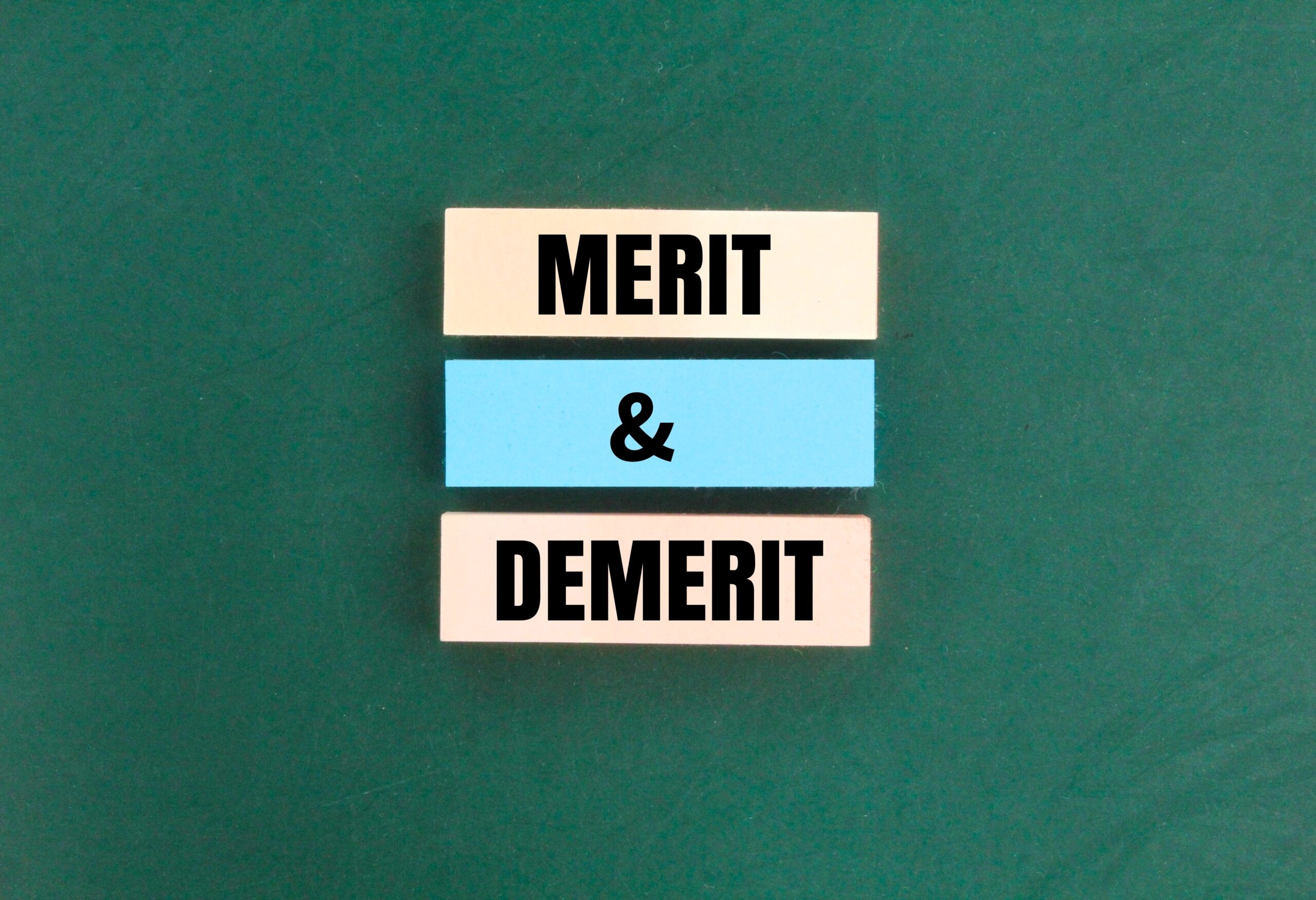FIT制度からFIP制度への移行、いわゆる「FIP転」は、再生可能エネルギー発電事業者にとって避けられない大きな転換点です。
市場価格に応じて収益が変動する仕組みは、収益拡大の可能性を広げる一方で、FIT制度の安定性を失うというデメリットも抱えています。
さらに、インバランス責任の発生や機器更新に伴う初期投資、アグリゲーター契約による手数料負担、そして制度変更リスクなど、事業運営における新たな課題が次々と現れます。
こうしたデメリットを正しく理解せずにFIP転を進めてしまうと、思わぬ収益悪化や追加コストに直面する恐れがあります。
本記事では、FIP転に伴う主なリスクとデメリットを整理するとともに、それを最小化するための戦略や事例を紹介しました。
発電事業者がFIP制度を上手に活用して持続可能な経営を実現するためには、デメリットを避けるのではなく「どう制御するか」が重要になります。
FIP転とは?制度の概要とFIT制度からの移行背景
FIT制度の安定性と限界
FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を大きく後押ししてきました。
一定期間、国が定めた価格で電力会社が必ず電気を買い取る仕組みであり、発電事業者にとっては収益の安定性が非常に高いのが特徴でした。
そのため、初期投資の大きい太陽光発電や風力発電でも事業計画が立てやすく、多くの新規参入を呼び込みました。
しかしFIT制度は、その安定性の裏で課題も抱えていました。
再エネの導入拡大に伴い、国民が負担する再エネ賦課金が急増し、電気料金の上昇を引き起こしました。
また、市場価格と切り離された固定価格での取引は、電力市場の競争性を損ない、系統安定化の妨げにもつながっていたのです。
FIP制度の仕組みと発電事業者に求められる責任
こうした背景から導入されたのがFIP制度(フィードインプレミアム制度)です。
FIPでは、発電事業者は電気を市場価格で販売し、その価格に国が定めた「プレミアム」が加算されます。
市場原理を取り入れることで、価格変動を事業者が直接受け止める一方、市場の安定化に寄与することが求められます。
そのため、FIP転を行った発電事業者は、単に発電して電気を売るだけではなく、発電計画と実績の差異に責任を持つ「インバランス責任」を負う必要があります。
さらに、需給調整市場や容量市場といった新しい市場への参入機会が広がる反面、その分だけ高度な予測や運用スキルが求められるのです。
なぜ今FIP転が進められているのか
FIP転が加速している背景には、日本のエネルギー政策の方向性があります。
再エネを「守られた電源」から「市場で競争できる電源」へ育てることが、今後のエネルギー政策の柱とされているのです。電力自由化が進むなか、FIT制度のような固定価格の仕組みは、長期的には持続不可能と判断されています。
また、再エネの大量導入によって系統不安定化が顕著になり、発電事業者が需給調整に責任を持つ必要性が高まっています。FIP転は、発電所が市場の一員として主体的にリスクを負担する仕組みであり、エネルギー政策の流れとして避けられない制度移行といえるでしょう。
FIP転の主なデメリット
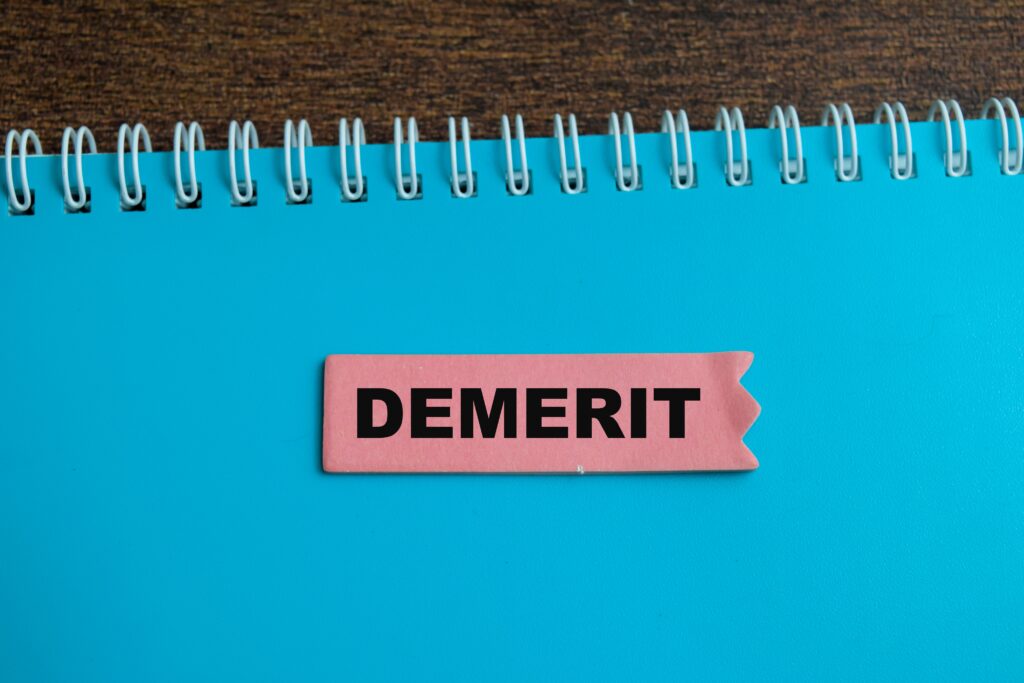
市場価格に左右される収益変動リスク
FIP制度に移行する最大のデメリットは、市場価格の変動が収益に直結することです。
FIT制度のように国が定めた固定価格で安定的に電力を買い取ってもらえる仕組みではなくなるため、発電事業者は電力市場の需給バランスや燃料価格の動向に強く影響を受けることになります。
例えば、再エネの大量導入が進んだ結果、昼間の太陽光発電が集中する時間帯に市場価格が大幅に下落するケースが増えています。
この時間帯にしか発電できない発電所では、プレミアムを加算しても収益が伸び悩み、FIT時代より利益が減少してしまう可能性があります。
逆に市場価格が急騰すれば収益拡大のチャンスとなりますが、それは保証されていません。
つまり、FIP転は「収益の上振れと下振れの両方にさらされる」という不確実性を抱えており、安定した収益を重視してきた事業者にとっては大きなリスクです。
インバランス責任によるコスト負担増加
もう一つの大きなデメリットは、インバランス責任を負う必要がある点です。
FIT制度では発電計画と実績がずれても電力会社がその責任を負っていましたが、FIP制度では発電事業者がその差分を一部負担する仕組みになっています。
再エネ発電は天候に依存するため、どうしても予測誤差が生じやすい電源です。
特に風力発電では、急な風況変化により発電量が短時間で大きく変動することもあり、その結果インバランスコストがかさんで収益を圧迫するケースがあります。
太陽光でも雲の流れや季節変動によって計画通りに発電できないことが多く、予測精度が低い発電所では安定収益を確保するのが難しくなります。
FIP転後は、インバランスコストを抑えるために高度な予測システムやモニタリング体制が必須となり、その分の負担も増えてしまうのです。
機器更新・通信設備・予測システム導入の初期投資
FIP制度に適応するためには、発電計画と実績を30分単位で提出することが求められます。
そのため、FIT時代に使用していた簡易的なメーターや監視システムでは要件を満たせないケースが多く、高精度のスマートメーターや通信設備への更新が必要になります。
さらに、AIを活用した発電予測システムやデータロガーの導入、クラウドでの監視体制構築など、追加投資が避けられません。
これらの設備投資は数百万円から数千万円に達する場合もあり、特に中小規模の発電事業者にとっては大きな資金的負担となります。
補助金制度を活用できれば負担軽減につながりますが、申請タイミングを逃せば全額自己負担になり、事業計画の採算性を大きく揺るがすリスクがあります。
アグリゲーター契約に伴う手数料や依存リスク
市場参加においては、ほとんどの発電事業者がアグリゲーターと契約せざるを得ません。
アグリゲーターは市場取引の代行や需給調整、インバランス対応などを担うため、その存在自体は不可欠です。
しかし、当然ながらアグリゲーターは手数料を徴収するため、収益の一部が差し引かれる形となります。
手数料率や契約内容はアグリゲーターごとに異なり、不利な契約を結んでしまうと収益性が大きく低下する恐れがあります。
さらに、アグリゲーターに過度に依存すると、自社での運営ノウハウが蓄積されず、将来的に制度が変わった際に柔軟に対応できなくなるというリスクもあります。複数のアグリゲーターを比較せずに契約したことで、想定以上の手数料や不十分なサポートに苦しむ発電所も実際に存在しており、選定の慎重さが問われるポイントです。
制度変更やプレミアム単価低下の不確実性
最後に、制度そのものの不確実性も無視できません。
FIP制度のプレミアム単価は固定ではなく、再エネ導入の進展や国の財政負担を背景に見直される可能性があります。
実際に、FIT制度でも買取価格は年々引き下げられてきた経緯があり、FIPのプレミアムも将来的に低下するリスクは十分に考えられます。
また、制度設計そのものもエネルギー政策や市場状況に応じて変更される可能性があります。
市場参加ルールの厳格化、インバランス負担割合の見直し、需給調整市場の制度改定など、事業計画に直接影響を与える変更が突然発表されることもあります。
長期的な事業安定を見込む発電所にとって、こうした制度リスクはFIP転を進める上で大きな不安要素です。
FIP転のデメリットを最小化する方法
蓄電池活用による価格変動リスクの回避
FIP制度の最大の不安材料は、市場価格に応じて収益が増減することです。
特に昼間に大量の電力が供給される太陽光発電では、市場価格が下がり収益が安定しないケースが多く見られます。この課題を解決する有効な方法が「蓄電池の活用」です。
発電した電力をそのまま売電するのではなく、価格の安い時間帯に蓄電池に貯めておき、価格が高い時間帯に放電して売電することで、市場変動リスクを緩和できます。
ピークシフト戦略を取ることで、プレミアム加算と高単価売電を同時に享受でき、収益の安定性と拡大を両立させられるのです。
高精度な発電予測でインバランスを抑える
FIP転後はインバランス責任が課され、発電計画と実績の差がコストとして請求されます。
このリスクを最小化するには、高精度な発電予測が不可欠です。
気象データや過去の発電実績をAIで解析するシステムを導入すれば、誤差を大幅に減らすことが可能です。
また、30分単位で発電計画を修正できる仕組みを整えることで、インバランス発生を抑制し、余計なコストを回避できます。
精度の高い予測体制は、単なるリスク軽減にとどまらず、アグリゲーターや市場からの信頼を高め、有利な契約条件を引き出す要素にもなります。
アグリゲーターを複数比較して最適契約を選ぶ
市場参加においてアグリゲーターの存在は不可欠ですが、その選定を誤るとコスト増や運営の硬直化を招きます。
契約前には、手数料体系・提供サービスの範囲・需給調整市場への参加実績などを複数社で比較することが大切です。
また、短期的なコストの安さだけではなく、長期的にどのようなサポートを提供してくれるのか、制度変更時に柔軟に対応できるかといった点も重要な判断基準です。
信頼できるアグリゲーターと組むことで、FIP転に伴うリスクを分散し、安定的な収益運営につなげられます。
補助金制度を利用して初期投資を軽減する
FIP転の導入には、高精度メーターや予測システム、蓄電池など大きな初期投資が必要となります。
この負担を軽減する手段が、国や自治体が用意している補助金制度の活用です。
国の蓄電池導入補助では導入費用の3割から5割を支援するものもあり、自治体独自の助成金を組み合わせれば、実質的な自己負担を大幅に削減できます。
補助金を計画的に利用することで、資金負担を抑えながらリスク対応のための設備を整えられる点は、FIP転のデメリットを解消するうえで欠かせない要素です。
事例で見るFIP転の課題と対応策

太陽光発電所での収益変動と蓄電池導入の効果
ある地方のメガソーラー発電所では、FIP転後に市場価格の下落によって収益が想定よりも低下する事態が発生しました。
特に昼間の安値が響き、FIT制度下と比べて利益が減少したのです。そこで導入したのが大規模蓄電池でした。
昼間の電力をためて夕方の高価格帯に売電するピークシフト戦略を取り入れることで、年間収益は従来比で15%増加。
FIP転によるリスクを逆にチャンスへと転換した事例です。
風力発電所における予測誤差とAIシステム導入事例
風力発電は天候によって発電量が大きく変動し、インバランスリスクが高い電源です。
ある風力発電所では、FIP転直後に予測精度の低さから多額のインバランスコストが発生し、収益性が大きく損なわれました。
そこでAIを活用した高精度予測システムを導入したところ、誤差が大幅に改善され、インバランスコストを半減することに成功しました。
結果として、プレミアム加算の恩恵を安定して受けられる体制を整え、FIP制度下でも持続的に運営できるようになったのです。
中小規模発電所が直面するアグリゲーター依存の問題
中小規模の発電所では、市場に直接参加するリソースがないため、アグリゲーターへの依存度が高まります。
ある中小規模の太陽光事業者は、契約条件を十分に比較せずにアグリゲーターと契約した結果、高額な手数料と不十分なサポートにより、期待した収益を確保できませんでした。
この事例は、アグリゲーター選定がFIP転後の事業収益を大きく左右することを示しています。
逆に、複数社を比較し、需給調整市場への参入実績や柔軟なサポート体制を持つアグリゲーターを選んだ発電所では、収益性が改善し、リスクを分散できた例もあります。
まとめ|FIP転のデメリットを理解しリスクを制御することが成功のカギ
FIP転は、再生可能エネルギー発電事業者にとって新たな収益機会を広げる制度である一方で、FIT制度では想定されなかった課題も少なくありません。
市場価格に左右される収益の不安定さ、インバランス責任による追加コスト、機器更新や予測システム導入に伴う初期投資の増加、アグリゲーターへの依存による制約、さらに将来的な制度変更やプレミアム単価の見直しといったリスクは、いずれも発電所の事業計画や資金繰りに直接的な影響を与える要素となります。
しかし、これらのデメリットは避けられないものではありません。
蓄電池を活用した価格変動リスクの回避、高精度な予測システムによるインバランス抑制、複数のアグリゲーター比較による最適な契約、さらには補助金制度を活用した初期投資負担の軽減といった対策を講じれば、リスクはコントロール可能です。
FIP転を成功させるカギは「デメリットを理解し、適切に制御すること」にあります。
制度を正しく理解し、現実的なリスク対応を行うことで、FIP転は単なる不安要素ではなく、収益拡大と持続可能な発電事業を実現するチャンスへと変わります。